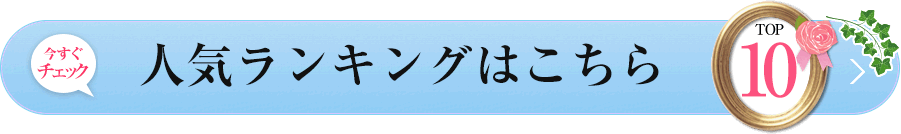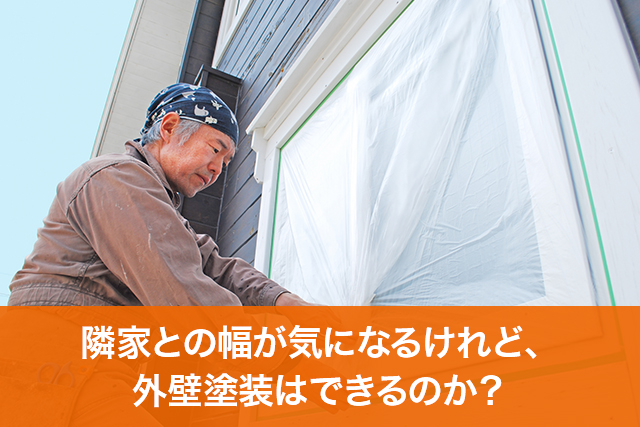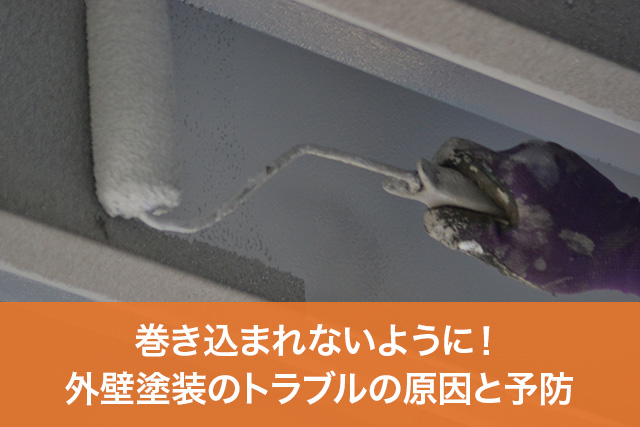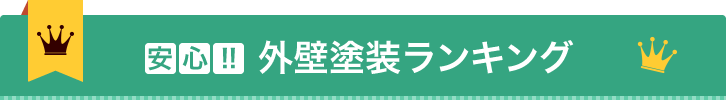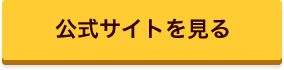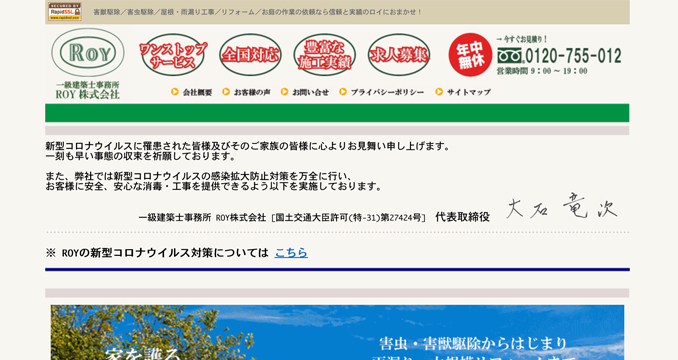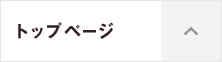コロニアルって知ってる?メンテナンスや耐久性を徹底解説


「コロニアル」という言葉を聞いて咄嗟になんのことか理解できる人は、少ないと思います。
結果からいいますと、「コロニアル」は新築住宅で最も用いられている屋根のことです。
そんな一番人気な屋根のことについて、今回はさまざまな観点から説明していきたいと思います。
コロニアルは、化粧スレートの商品名です。
しかし、一般名称になりつつあるため、薄型スレート瓦を統一してコロニアルと表現することも多いです。
そんなコロニアルについて耐久性やメンテナンス時期など、ここから解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
見出し
コロニアルってどんなもの
コロニアルは、カラーベストやスレート屋根などとよばれています。
統一されてはいません。
厳密にいえば、それぞれ違うものなのですが、どの名称も同じ意味と捉えていただいて大丈夫です。
それぞれを具体的に説明していきます。
スレート瓦
スレート瓦は、セメントや粘土などをもとにつくられた瓦のことです。
コロニアルは、薄い板のスレート瓦に分類されており、「薄型(化粧)スレート瓦」とも呼ばれています。
反対に、厚いスレート瓦は「厚型スレート瓦」と呼ばれています。
スレート瓦は歴史が古く、昔は主な素材が石綿(アスベスト)であったため「石綿スレート瓦」とも呼ばれていました。
そのこともあり、「スレート瓦はアスベスト」というイメージが定着している人も多くいます。
現在は、アスベストの使用が禁止されているのですが、スレート瓦にネガティブなイメージがついてしまったため、スレート瓦のことを「カラーベスト」や「コロニアル」という名称で呼ぶようになったのです。
カラーベスト
アスベストが含まれていないスレート瓦が販売開始され、これが「カラーベストシリーズ」です。
カラーベストシリーズには、品質や形状など種類が豊富でたくさんのラインナップがあります。
コロニアル
カラーベストの中で、一番人気があり使用されているのが「コロニアル」です。
コロニアルは、ケイミュー(旧クボタ松下電工外装株式会社)が販売する屋根瓦の商品名・ブランド名のこと指します。
コロニアルが人気になった理由
現在、新築の住宅で最も人気がある屋根材がコロニアルです。
コロニアルは登場とともに爆発的に普及したのですが、それには5つの理由があるといわれています。
それが…
●他の屋根材よりも価格が安い
●施工が簡単なので工期が短くなる
●粘土瓦よりも軽い
●カラーバリエーションが豊富
●太陽光発電装置が設置できる
コロニアルは、セメント基材とパルプ繊維が強く結合されて出来ている素材です。
先述したように、昔はパルプ繊維の代わりに石綿(アスベスト)が使われていました。
現在では、石綿に代わり補強用の超微粉末材によって、さらに強い粘りと耐久性を備えることになりました。
しかし、アスベスト規制直後時期に販売されたスレート瓦には、不具合があるものも多く報告されています。
コロニアルと石綿(アスベスト)
ほとんどの戸建て住宅が石綿スレート
現在、存在する戸建て住宅のスレート瓦のほとんどが石綿スレートです。
日本の建築材で使用されているアスベスト全体の64%以上は石綿(アスベスト)スレート瓦です。
アスベストの使用禁止が法規制で強化されたのが平成18年9月1日です。
さらに平成24年の改定で、従来ならば1%以下の含有規制だったのですが、アスベストは一切禁止になりました。
そのため、平成18年以前、平成18年から平成24年の改定までに建築または増築された住宅の屋根には石綿(アスベスト)が含まれている可能性が高いです。
健康被害はどうなのか
上記のほとんどの住宅の屋根には、アスベストが含まれているということを知って不安を募らせている人もいるかもしれませんが、安心してください。
現在流通している石綿スレート瓦のほとんどが非飛散性です。
固められているため、アスベスト粒子が飛び散ることはありません。
ですが、雨漏りなどが生じている場合や、目で確認できるほどの経年劣化が発生している場合、そこからアスベスト粒子が飛散する可能性はあります。
しかし、このことが健康に悪影響をもたらすかは科学的に判明していません。
石綿スレート瓦のメンテナンス
石綿スレート瓦のメンテナンス方法は主に2種類あります。
解体処分する
1つ目は既存の石綿スレート瓦を解体処分する方法です。
解体処分は、費用が高額で作業ができる業者にも限りがあります。
解体するには資格を保有していなければならなくて、業者は「石綿作業主任者」「特別管理産業廃棄物管理責任者」「アスベスト診断士」などが必要になります。
産廃処理業者は、「マニフェストの作成」や「登録免許」が必要になります。
そのため、アスベスト含有のコロニアルを解体処分するには、高額な費用と長期間の工事が必要になるので、ほとんどおこなうことがありません。
カバー工法(封じ込め)
もうひとつが既存のコロニアルを残したまま金属屋根を上から張るカバー工法です。
コロニアルの上に金属屋根を葺くことで、アスベストが含まれているコロニアルを封じ込めることができます。
耐久性と軽さを兼ね備えた金属屋根だからこそ可能な工法で、今もっとも主流なコロニアルのリフォーム方法です。
耐用年数とメンテナンス時期は?
メンテナンスのスケジュールを管理する方法は、年月と目視です。
年月によるメンテナンスの時期
屋根の部分補修メンテナンスは、10年に1度が推奨されています。
さらに30年を超えたコロニアルは寿命ということで、葺き替えなど屋根工事の依頼検討を推奨しています。
目視によるメンテナンスの時期
コロニアルは、目視による確認で劣化状況を確認することができます。
状況としては3段階に分かれていまして、「色褪せ」「塗膜剥離」「基材湿潤、凍害」になります。
それぞれの劣化状況について説明していきます。
色褪せ
紫外線や雨水などの外的要因によって塗料がチョーキングを起こす症状です。
手で触れるとチョークの粉のようなものが付着します。
塗膜剥離
塗膜劣化が促進して、基材表面も劣化して塗膜の表面が剥がれてくる症状です。
基材湿潤
塗膜の剥離を放置してしまうと、基材に水分が浸入してしまい、そのことで膨張して破壊へとつながってしまいます。
基材湿潤が発生している段階まで進んでしまうとコロニアルが激しく反り、強度もかなり弱っているおそれがあります。
ここまできてしまうと、葺き替えでしかメンテナンスができないので注意が必要です。
まとめ
コロニアルについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
読んでいく途中に不安にかられるところもあったかもしれませんが、問題ありません。
しっかりとメンテナンス時期を抑えて手入れを依頼すれば、大丈夫です。
依頼できる業者に限りがあるため、じっくりと候補を探し、自宅の屋根についてもしっかりと把握しておきましょう。